-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
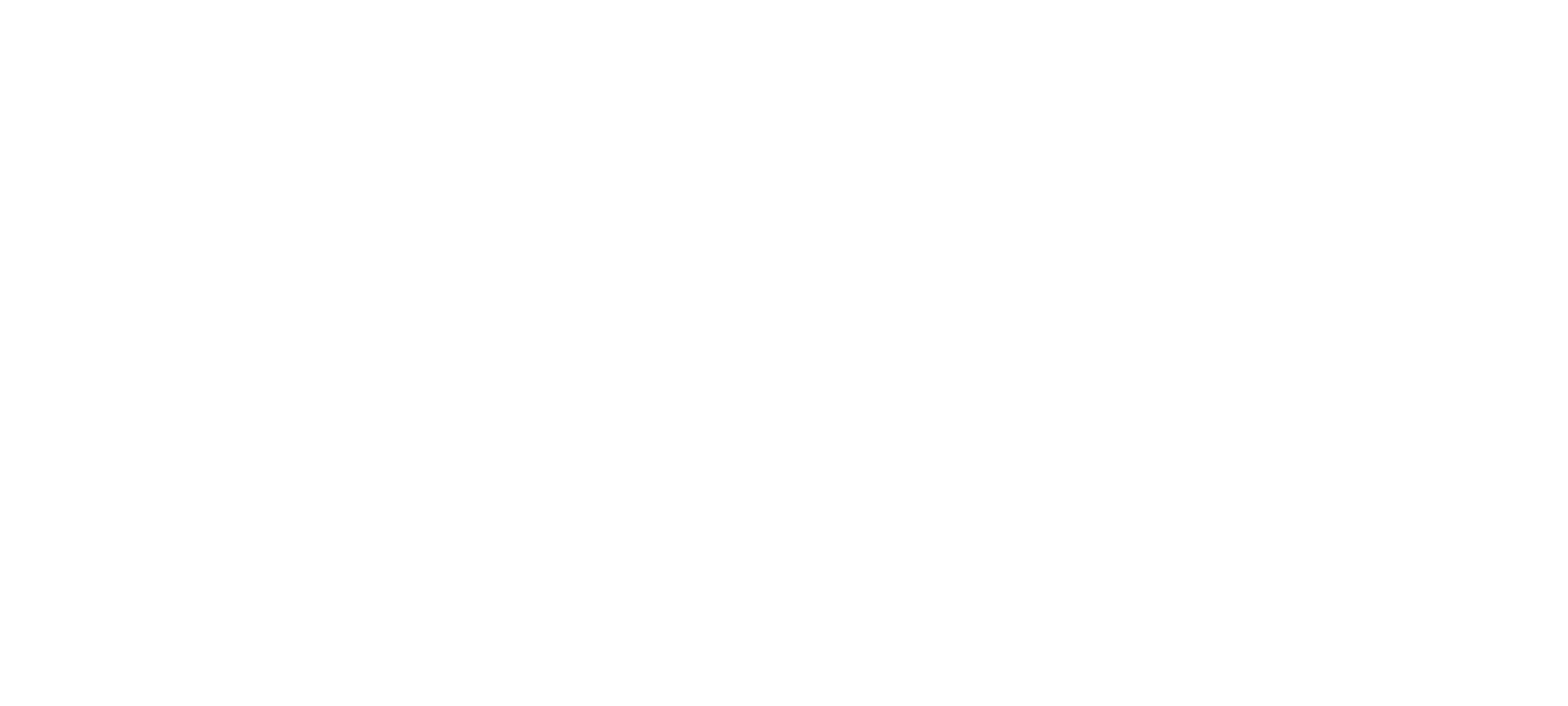
みなさん、こんにちは!
10月も下旬に差し掛かり、気温がぐっと下がってきましたね。
秋が本格化するこの時期、最も楽しみなイベントといえば「紅葉狩り」ではないでしょうか?赤や黄色に染まった山々の景色は、本当に美しいですよね(´ω`)
日本全国で紅葉スポットが話題になるこの季節、今年こそ素敵な秋を満喫したいと考えている方も多いと思います。
というわけで今回は、秋の紅葉狩りを楽しむためのスポット情報をご紹介いたします。計画を立てるときの参考にしていただければと幸いです。
1.全国で最も早い紅葉は北海道から始まる
紅葉のシーズンは、北から南へと長く続きます。北海道の大雪山系では例年9月下旬から紅葉が始まり、10月上旬がピークとなります。北海道内でも標高の高い場所から低い場所へ、時間をかけて紅葉が進んでいくため、長期間にわたって楽しむことができるんです。
一方、本州の高地では10月中旬から、平地では11月に入ってからが見頃となります。同じ日本でも場所によって色付くタイミングが大きく異なるため、自分の計画に合わせて訪問先を選ぶことができるのは、紅葉狩りの大きな魅力です。
2.紅葉の色は天気で変わる?撮影のコツ
紅葉の美しさは、撮影する時間帯や天気によって大きく変わることをご存知ですか?晴天の日中に撮ると、紅葉の赤が鮮烈に映り、コントラストのある写真が撮れます。一方、曇りの日は全体的に柔らかい印象になり、紅葉全体の雰囲気を生かした写真が撮れます。
また、早朝の光が紅葉を透かすように照らす時間帯は、背景との相乗効果で幻想的な雰囲気が生まれます。同じ紅葉でも、見る角度、時間帯、天気によってまったく違う表情を見せてくれるのです。
複数回訪問できるなら、異なる時間帯や天気の日に訪れることで、より多くの紅葉の魅力を発見できるでしょう(^^)/~~~
3.紅葉狩りの穴場スポット探しのコツ
有名な観光地は美しい紅葉が見られる反面、混雑がひどいことも多いですよね。人気が集中する場所を避けたい場合は、地元の観光案内所に相談したり、地域のブログで情報を探したりするのがおすすめです。
また、寺社仏閣の庭園は、比較的人が少なく、整えられた庭園の中で落ち着いて紅葉を鑑賞できることが多いです。さらに、小規模な公園や里山の散策路なども、穴場スポットとして知られています。
こうした場所なら、自分のペースで、ゆっくりと秋を感じることができます。紅葉狩りは、有名だからといって必ずしも最高体験とは限りません。自分たちだけの特別な秋風景を見つけることも、紅葉狩りの醍醐味なのです。
いかがだったでしょうか?
今年の秋を彩る紅葉狩りの情報をご紹介しました。見頃の時期は年によって変わるため、出かける前に最新の開花情報をチェックすることをおすすめします。また、10月から11月は気温の変動が大きいため、服装選びにも注意してくださいね。家族と、友人と、恋人と、秋の美しさを共有する時間は、本当に特別なものになるでしょう。今年の秋も素敵な思い出をたくさん作ってくださいね!
紅葉狩りを楽しんだ後は当方にもお立ち寄りください。ほっこりする思い出話を楽しみにしています!
みなさん、こんにちは!
9月といえば、夜空がきれいに見える季節ですね。空気が澄んできて、お月様もひときわ美しく輝いて見えます。そんな9月の大きなイベントといえば「お月見」!今回は、お月見の由来や楽しみ方について詳しくご紹介します♪
今年の中秋の名月はいつ?
2025年の中秋の名月は10月6日です。「中秋の名月」とは、旧暦8月15日の夜に見える月のことで、「十五夜」とも呼ばれます。実は、中秋の名月の日付は毎年変わるんです。これは、現在私たちが使っている新暦と、昔使われていた旧暦にズレがあるためなんですね。
お月見の由来って?
お月見の習慣は、平安時代に中国から伝わったとされています。もともとは貴族の間で、美しい月を眺めながら詩を詠んだり、音楽を楽しんだりする風雅な行事でした。その後、江戸時代になると庶民の間にも広まり、収穫に感謝する行事として定着しました。お米や里芋などの収穫時期と重なることから、「芋名月」とも呼ばれているんですよ。
お月見の楽しみ方いろいろ
現代でも、お月見を楽しむ方法はたくさんあります。まず定番は月見団子ですね。白い丸い団子を作って、ピラミッド型に積み上げてお供えします。15個または12個(その年の月数)作るのが一般的です。手作りが面倒な方は、市販のものでももちろんOKです(^^)/~~~
ススキを飾る意味
お月見といえばススキも欠かせませんね。ススキは稲穂に似ていることから、豊作への願いを込めて飾られるようになりました。また、ススキの鋭い葉には魔除けの効果があると信じられていたんです。近所でススキを見つけたら、ぜひお月見の飾りつけに使ってみてください。
現代風お月見アイデア
最近では、月見バーガーや月見うどんなど、現代風にアレンジしたお月見グルメも人気ですね。ベランダやお庭で月を眺めながら、お気に入りのお茶やコーヒーを飲むのも素敵です。写真撮影が趣味の方は、月の撮影にチャレンジしてみるのもいいでしょう。
いかがだったでしょうか?
忙しい日常の中で、たまには空を見上げて月を眺める時間を作ってみませんか?お月見は、自然の美しさを感じ、季節の移ろいに心を向ける素晴らしい機会です。家族や友人と一緒に、今年のお月見を楽しい思い出にしてくださいね(´ω`)
みなさん、こんにちは!
8月といえば、やっぱり夏祭りと花火大会ですよね。最近は各地で素敵なイベントが開催されていて、見どころがいっぱいです。今年はどこに行こうかなと迷っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、夏祭りと花火大会の楽しみ方について、ご紹介したいと思います。せっかくの夏のイベントですから、思いっきり楽しんじゃいましょう (^^)/
夏祭りの醍醐味といえば屋台グルメ!
夏祭りに行ったら、まずは屋台巡りから始めませんか?たこ焼き、焼きそば、かき氷、りんご飴など、定番のグルメがずらりと並んでいる光景は、見ているだけでワクワクしてきます。
最近は地域色豊かな屋台も増えていて、その土地ならではの味を楽しめるのも魅力の一つです。静岡の富士宮焼きそばや、大阪のイカ焼きなど、旅行先で出会える特別なグルメもあります。
屋台で食べる料理って、なんだかいつもより美味しく感じませんか?それは祭りの雰囲気や、みんなで一緒に食べる楽しさが味をより引き立てているからかもしれません。家族や友人と一緒に「これ美味しいね」なんて言いながら食べ歩くのは、夏の特別な思い出になりますよ。
浴衣で楽しむ夏祭り
夏祭りといえば、浴衣を着て参加するのも楽しみの一つです。最近は男性も浴衣を着る方が増えていて、カップルでお揃いの浴衣を着てお出かけする姿もよく見かけます。
浴衣を着る時のポイントは、歩きやすさを重視することです。下駄は慣れていないと足が痛くなることがあるので、履き慣れた靴やサンダルを持参するのもおすすめです。また、浴衣用のバッグは小さめなので、必要最低限の荷物で身軽にお出かけしましょう。
髪型も浴衣に合わせてアレンジすると、より一層素敵に見えます。簡単なアップスタイルやお団子ヘアで、涼しげな印象を演出してみてください。
花火大会の見どころと楽しみ方
夏祭りとセットで楽しめるのが花火大会です。大きな花火大会では、音楽に合わせて打ち上げられるスターマインや、フィナーレの連続花火など、見応えのあるプログラムが用意されています。
花火大会を楽しむコツは、事前の準備にあります。レジャーシートや折りたたみ椅子を持参して、ゆっくりと座って鑑賞できるスペースを確保しましょう。また、虫除けスプレーや飲み物も忘れずに持っていくと安心です。
花火の音って、会場にいると体に響いてくるんですよね。その迫力は、テレビやスマートフォンでは味わえない特別な体験です。特に大きな花火が打ち上がる瞬間の「ドーン」という音と、夜空に広がる美しい光の瞬間は、何度見ても感動してしまいます
(* ´∀`*)
地域の特色を楽しもう
各地の夏祭りには、その地域ならではの特色があります。青森のねぶた祭りや仙台の七夕祭り、京都の祇園祭など、歴史と伝統を感じられる大きなお祭りもあれば、地元の小さな神社で開催される温かみのあるお祭りもあります。
地域の特色を知ると、お祭りの楽しみ方も変わってきます。その土地の歴史や文化を事前に調べてから参加すると、より深くお祭りを楽しめるでしょう。
安全に楽しむために
夏祭りや花火大会を楽しむ際は、安全面にも気を配りましょう。人混みでは迷子にならないよう、家族や友人と待ち合わせ場所を決めておくことが大切です。
また、暑い時期のイベントなので、熱中症対策も忘れずに。こまめな水分補給と適度な休憩を心がけて、体調管理に注意しましょう。
夏祭りと花火大会は、日本の夏の風物詩として多くの人に愛され続けています。今年の夏も、家族や友人と一緒に素敵な思い出を作ってくださいね。
お出かけ帰りには私たちも会いに来ていただけるととても嬉しいです。お土産話を楽しみにしています!
素敵な夏になりますように (´∀`)
みなさん、こんにちは!
ゴールデンウィークが明けて、なんだか気分が上がらない…体もだるいしやる気も出ない…。そんな風に感じること、ありませんか?それ、もしかしたら「五月病」かもしれません(;・∀・)
五月病とは、新年度の緊張が一段落した5月頃に、やる気の低下や疲労感、うつうつとした気分を感じること。特に、進学・就職・異動などで環境が変わった方は要注意です!
というわけで今回は、五月病を吹き飛ばす「心と体のセルフケア法」をご紹介します♪
【心のケア:無理せず“ちょっとサボる”】
「しっかりしなきゃ」と自分にプレッシャーをかけすぎていませんか?真面目な人ほど五月病になりやすいとも言われています。まずは「まぁいっか」と思える心の余白を大切に。
おすすめは、寝る前にスマホを置いて5分間だけ目を閉じて呼吸に集中する“プチ瞑想”です。呼吸に意識を向けるだけで、心がすーっと静かになって、自然と気持ちも軽くなりますよ(
?ω? )
他にも、日記をつけて思っていることを言葉にするのもおすすめです。頭の中でモヤモヤしていたことが整理されて、少しだけ気持ちが楽になることがあります。映画を観て思い切り泣く「涙活」も意外と効果的だったりします。
【体のケア:ストレッチとハーブティーでリラックス】
座りっぱなしの時間が長いと、自律神経が乱れがちに。そんなときは、簡単な肩回しや背伸びのストレッチをして、血流をよくしてあげましょう!
また、寝る前におすすめなのが「カモミールティー」や「ラベンダーティー」などのハーブティー。自然な香りで心も体もほっと一息つけます。お気に入りのマグカップを使うのも、気分転換になって◎
お風呂に入る際、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのも有効です。お気に入りの入浴剤を使えば、心も体もふんわりとほぐれます。
【食生活も一役!】
ビタミンB群やたんぱく質を意識した食事を心がけて、腸内環境を整えるとメンタルも安定します。ヨーグルトや納豆、野菜スープなど、身近なものから始めてみてくださいね。
旬の食材を取り入れるのも効果的です。春キャベツや新玉ねぎなど、今の季節ならではの野菜を使って、体の中からリセットしていきましょう。できる範囲で「温かい食事」を心がけると、消化も良くなり体調も整います。
気分が乗らない日は、無理せず「今日はちょっとゆっくりしよう」と自分に優しくしてあげましょう。完璧じゃなくても大丈夫。五月病は誰にでも起こりうる自然な反応です。
深呼吸して、空を見上げて、小さなリセットを重ねながら、少しずつ日常に戻っていきましょうね(´∀`) みなさんの5月が、少しでも穏やかに過ごせますように。
それでも気分が晴れない時は働く場所を変えるのも良いと思います。
ひょっとすると私たちの会社でなら充実した毎日を送ってもらえるかもしれません。
少しでも興味が湧いたならどうぞお気軽にお問い合わせください!
みなさん、こんにちは!
春本番の4月がやってきて、あちこちから桜の便りが届き始めましたね。お弁当を持って花見に行ったり、家族や友人と桜並木を散歩したり、春はイベントがめじろ押しですが、お出かけの際は天気予報もチェックして、急な雨に備えることをお忘れなく~☆
春の風物詩といえばやはり「桜」ですよね!
ということで今回は、桜にまつわる豆知識をご紹介します。せっかく桜を楽しむなら知識をつけて楽しんでいきましょう(^^)/~~~
1.桜前線って何?
桜前線とは、桜(主にソメイヨシノ)の開花日を結んだ線のことです。通常、南から北へと桜の開花が進むため、その様子を天気図の前線のように表したものなんです。気象庁が毎年発表していて、春の訪れを知らせる指標として親しまれています。
桜の開花は気温と深い関係があり、平均気温が約10度を超えるとつぼみが膨らみ始め、約15度になると開花する傾向があるそうです。だから温かい南から順番に咲いていくわけですね。
2.桜の種類はどれくらいあるの?
日本には実はとっても多くの桜の品種があるんです!一般的に知られているソメイヨシノの他にも、八重桜、枝垂れ桜、山桜などが有名ですが、実は日本に自生する野生種だけでも約10種類、園芸品種を含めると約200種類以上もあるんですよ。
ソメイヨシノは江戸時代末期に作られた園芸品種で、実はクローン同士なんです!だから全国どこでもほぼ同じ時期に咲きますが、他の品種は開花時期がバラバラで、早咲きの河津桜から遅咲きの八重桜まで、2月から5月まで長く桜を楽しむことができます。春の楽しみが長続きするのはうれしいですね(^^)
3.桜と花見の歴史は?
日本の花見の歴史は古く、平安時代に貴族の間で梅を愛でる風習があったのが始まりです。その後、鎌倉時代から桜の花見が主流になっていきました。江戸時代には将軍・徳川吉宗が上野公園などに桜を植えさせ、一般庶民にも花見を楽しめる場所を提供したことで、花見が大衆文化として広まりました。
当時は「春を祝う」という意味だけでなく、その年の豊作を祈る農耕儀礼としての意味も持っていたんですよ。花見の席で食べる「花見団子」や「花見酒」の習慣もこの頃から始まったそうです。歴史と共に歩んできた桜と花見、今年の春も大切な人と一緒に楽しみたいですね~ヽ(´▽`)/
いかがでしたでしょうか?
今回は、春本番の4月にぴったりな桜にまつわる豆知識をご紹介しました。桜の美しさをより深く味わえるよう、この知識を持って今年の花見に出かけてみてください。桜の楽しみ方は一つじゃない、ということで、今年の春も家族と、友人と、大切な人と、存分に満喫してくださいね!
春の思い出、たくさん作っていきましょう(^▽^)
私たちにも素敵な思い出をシェアしていただけるととても嬉しいです。
ご来店をお待ちしています!
みなさん、こんにちは!
寒い冬も終わりに近づき、そろそろ春の花々が咲き誇る季節がやってきますね。今回
は、春一番に咲く梅から始まる、花々のリレーについてお話ししたいと思います!
まずは梅の花から。真冬の寒さの中でも凛と咲く姿は、まさに「春の訪れ」を告げる
使者のよう。白や紅の花びらが寒空に映える様子は、どこか凛々しさを感じさせます
よね。梅の香りを楽しむ「梅香る」という言葉があるように、香りも楽しみの一つ。
特に朝もやの立ち込める早朝に梅林を散策すると、幻想的な雰囲気を味わえますよ
(*^^*)
実は梅の品種は1,000種類以上もあるんです!有名な「白加賀」は大ぶりで香り高
く、「冬至梅」は12月から咲き始める早咲きの品種。「野梅」は小ぶりながらも強い
香りを放ち、「緑萼梅」は珍しいがくの色が特徴的です。それぞれに個性があって、
梅の魅力を何倍も深めてくれますね。
そして春の七草!「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すず
しろ」と言われる七種の若菜には、邪気を払い、一年の健康を願う意味が込められて
います。最近では七草粥を食べる習慣が少なくなってきましたが、春の野菜を取り入
れて体調を整えるという知恵は、現代にも通じるものがありますね。実は、これらの
七草にはそれぞれ栄養学的な意味もあったんです。ビタミン類が豊富で、冬の間不足
しがちだった栄養を補給してくれる、先人の知恵が詰まった組み合わせなんですよ。
春を告げる花といえば、水仙やクロッカスも忘れられません。まだ寒い季節に、凛と
咲く姿は勇気をくれます。特に日本水仙は、寒風に揺れながらも芳香を漂わせ、心を
和ませてくれますよね。最近では、これらの球根を室内で育てて楽しむ「フォーシン
グ」という方法も人気です。暖かい部屋の中で、一足早い春を感じられるんですよ
(^^)
そして徐々に桜の季節へ…。気象庁から発表される桜前線の情報に、心が躍りませ
んか?開花予想日が発表されると、お花見の計画を立てる人も多いはず。実は桜の開
花には「開花日」と「満開日」があって、開花から満開までは約1週間。この時期の
寒暖差によって開花スピードが変わるんです。
お花見の準備も大切ですよね!定番のブルーシートやお弁当はもちろん、最近は折り
たたみチェアやモバイルバッテリーなど、快適に過ごすためのアイテムも増えてきま
した。夜桜を楽しむなら、暖かい飲み物を入れた魔法瓶があると安心です。
意外と知られていませんが、桜前線の発表には「標本木」という特別な木が使われて
いるんです。各地域で選ばれた標本木の様子を観察して、開花予想が立てられていま
す。東京の場合、靖国神社にある標本木が有名。毎年多くの人が、この木の様子に注
目しているんですよ\(^o^)/
そして、桜の開花を待つ間にも、色々な花が私たちの目を楽しませてくれます。黄色
いパンジーやビオラ、チューリップの芽吹き、早咲きの木蓮…。春の訪れは、こん
なにもたくさんの花々がリレーのように咲き継いで教えてくれるんです。
さあ、みなさんも身近な場所で、春の訪れを探してみませんか?小さな花々との出会
いが、きっと素敵な春の思い出になるはずです。
春の予感に誘われたなら、もう少しだけ足を伸ばして私たちにも会いに来ていただけ
るととても嬉しいです!
お会いできるのを楽しみにしています!
みなさん、こんにちは!
まだまだ寒い日が続きますが、暦の上ではもう春。今回は、立春から始まる春の訪れについてお話ししていきますね(^^♪
立春は二十四節気の一つで、暦の上で春が始まる日。旧暦では、立春が1年の始まりとされていました。「春立つ」という言葉には、春が動き始める、目覚めるという意味が込められているんです。
「立春大吉」という言葉を聞いたことがありますか?立春の日に、この四文字を書いて飾ると縁起が良いとされています。また、立春朝搾りという習慣も。立春の朝一番に搾った生醤油は、特に縁起物として重宝されてきました。このように、立春には新しい季節を迎える様々な風習が残されているんですよ。
立春を過ぎても、まだまだ寒い日が続きますよね。でも、よく観察してみると、確実に春の気配が感じられるんです。例えば、朝日が昇る位置が少しずつ北に移動したり、日の入り時間が遅くなったり。小さな変化に気づくと、春の訪れがより楽しみになりますよ。
2月の代表的な春の便りと言えば、梅の花。寒さに強い梅は、まだ寒い時期から咲き始めます。紅梅、白梅と色とりどりに咲く様子は、春の訪れを一番に告げる風物詩。梅の香りには、邪気を払う効果があるとされ、古くから日本人に愛されてきました(*^^*)
梅にまつわる言葉も素敵なものがたくさん。「寒梅」は厳しい寒さの中で咲く梅のこと。「青梅」はまだ若い梅の実で、梅干しや梅酒の原料になります。梅は、花も実も香りも、私たちの暮らしに寄り添ってくれる植物なんです。
菜の花も、早春を彩る花の一つ。黄色い花が一面に広がる様子は、春の陽気そのもの。菜の花には、新芽が出る、芽吹くという意味の「な(菜)」が含まれています。その名の通り、春の生命力を感じさせる花なんです。
鳥たちの様子も変わってきます。ウグイスのさえずりが聞こえ始めたり、渡り鳥が北へ帰る準備を始めたり。春を待つ小鳥たちの姿に、心が和みますね。最近では、メジロやヒヨドリが梅の花を求めて庭に訪れることも。小鳥たちの様子を観察するのも、春の楽しみの一つです。
伝統行事でも、春の訪れを祝います。「初午(はつうま)」は、2月最初の午の日に行われる稲荷神社のお祭り。商売繁盛や家内安全を願って参拝する人で賑わいます。神社では、おいなりさんの形をした縁起物や、春を告げる梅の枝が販売されたりもします。
各地の梅まつりも、春の訪れを告げる行事として人気。偕楽園や湯河原梅林など、名所では早咲きから遅咲きまで、様々な品種の梅を楽しむことができます。夜間のライトアップや、野点(のだて)なども開催され、梅の香り漂う中でお茶を楽しむ風情は格別です(^ω^)
暖かい春が待ち遠しい季節。でも、この寒さの中にも確実に春は近づいています。少しずつ変化する自然の様子を楽しみながら、春の訪れを待ちましょう。日々の暮らしの中で、春の気配を見つける楽しみを、ぜひ味わってくださいね!
春は新しいことを始めるのに良い季節です。新しい世界に飛び込んでみませんか?
いま私たちは一緒に働く仲間を募集しています。ホームページをご覧になって少しでも興味が湧いたならどうぞお気軽にお問い合わせください。
楽しみにお待ちしています!
みなさん、こんにちは!
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね(^o^)丿
年が明けると、さまざまな伝統行事が待っていますよね。どれも由緒ある行事なので
すが、ただ何となく参加しているという方も多いのではないでしょうか?そこで今回
は、お正月の伝統行事について、その意味や由来をご紹介していきます!
まずは、初詣からスタート!初詣は、その年の無事と幸せを願って神様にご挨拶に行
く大切な行事です。多くの方が元日に行かれると思いますが、実は1月1日〜1月7日ま
でが松の内と呼ばれる期間。この間であれば、いつ行っても「初詣」になるんです
よ。混雑を避けて、2日以降に行くのもおすすめです。
初詣の参拝方法も、きちんと押さえておきたいポイントです。鳥居をくぐる前に一
礼、参道は端を歩き、中央は神様の通り道。手水舎での清め方は、左手で柄杓を持
ち、右手を清め、次に右手で柄杓を持ち直して左手を清めます。その後、左手に水を
受けて口を清め(飲んだ水は飲み込まず脇に吐き出します)、最後に柄杓を立てて柄
を清めます。
次は初日の出!新年を告げる朝日を拝むことには、太陽神である天照大御神を敬う意
味が込められています。最近では、初日の出クルーズやスカイツリーなどの展望台で
の観賞も人気ですね。ご自宅のベランダや近所の高台でも、ゆっくり朝日を拝むこと
ができますよ。気象庁のウェブサイトで日の出時刻を確認して、少し早めに目的地に
到着するのがおすすめです(*^^*)
そしてお待ちかねのおせち料理!黒豆は「まめに暮らせますように」、数の子は「子
孫繁栄」など、一つ一つの料理に縁起の良い意味が込められています。田作りは五穀
豊穣、昆布巻きは「喜び」を表すなど、実は知らない意味がたくさん。最近では、和
洋折衷のおせちや、一人用のミニおせち、オードブル形式のパーティーおせちなど、
ライフスタイルに合わせた楽しみ方も増えてきましたね。
伝統的なおせちを全て手作りするのは大変ですが、一品だけでも作ってみるのはいか
がでしょうか?黒豆や煮しめなど、基本の作り方を覚えておくと、普段のお料理の幅
も広がりますよ。
最後は1月7日の七草粥です。お正月のごちそうで疲れた胃腸を休めるという実用的な
意味と、春の七草を食べて無病息災を願う意味があります。七草は「せり、なずな、
ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」。スーパーでも七草セットが
売られているので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!七草粥を食べながら、「唐
土の鳥が日本の正月に、渡らぬ先に、七草なずな」と唱えるのも粋な楽しみ方です
(^−^)
お正月の伝統行事には、先人たちの知恵と願いが詰まっています。形を変えながら
も、大切に受け継がれてきた行事を、現代の暮らしに合わせて楽しんでいきましょ
う!
お正月の行事を楽しんだ後は、気持ちを新たにこれからの1年の過ごし方に想いを馳
せてみてはいかがでしょうか。そのために私たちは快適な時間を提供できればと思い
ます。
良い計画を思いついたら私たちにも教えてください!お会いできるのを楽しみにして
います^^
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
みなさん、こんにちは。
秋も深まり、森や山々が赤や黄色に染まり始めましたね。そんな秋の訪れを感じられ
るのが、何と言っても美味しい季節の食材を味わうこと!今回は、11月に旬を迎える
食材をご紹介したいと思います(`・ω・´)ゞ
□■ 松茸 – 秋の贅沢♪ ■□
秋の風物詩の代表選手と言えば、この「松茸」ですね。深い森の中で育つこの珍しい
食材は、まさに秋の贅沢。独特の芳香と、柔らかい食感が魅力です。
松茸は、主に10月上旬から11月にかけて収穫期を迎えます。産地では丁寧に手摘みさ
れ、新鮮なうちに市場に出回ります。その味わいは格別で、炭火焼きや土瓶蒸し、天
ぷらなどで楽しめます。贅沢な逸品ですが、秋ならではの味覚を存分に堪能できるで
しょう。
□■ サンマ – 秋刀魚の美味しさ ■□
秋の味覚と言えば、抜群の脂ののったサンマ(秋刀魚)も外せません。脂がのりに乗
り、焼いたときの香ばしさが堪らない逸品です。
サンマの旬は10月頃から11月にかけて。北海道や三陸沖で獲れたての新鮮なサンマ
は、塩焼きや干物、煮付けなど、様々な調理法で楽しめます。特に、身がプリプリで
脂がのったサンマを塩焼きにすると、身がふっくらとした食感と、口の中でとろける
ような味わいが堪能できます。
こうしたサンマを秋の夜長に頬張るのは、とても贅沢な気分を味わえるはずです。
□■ 栗 – 心も体も温まる ■□
秋の味覚の定番といえば、やはり「栗」ですね。栗は10月中旬から11月にかけが旬を
迎えます。
栗は、焼き栗や栗ご飯、渋皮煮など、さまざまな調理法で愉しめる食材。香ばしさと
甘みが特徴で、体も心も温まる味わいです。
中でも、炉端で焼いた栗は格別。外はパリッと香ばしく、中はホクホクとした食感が
堪能できます。お酒のおつまみにもぴったりですね。
また、栗は旬の時期にしか味わえない食材。その季節感を感じられるのも、秋 なら
ではの魅力です。
□■ 秋の行事とコラボ ■□
さらに、秋の食材は、月見やお月見団子などの行事とも密接に関わっています。
例えば、十五夜の月見の定番グルメは、お月見団子。丸い形が満月を表すこの和菓子
には、栗が良く合います。また、ほっくりとした食感がホッと心に沁みわたるでしょ
う。
また、十日夜(11月10日)の「三月見」の際にも、松茸や栗を使った行事食が登場しま
す。自然の移ろいを感じながら、温かな団らんの時間を過ごせるのが魅力ですね。
このように、秋の食材は単に美味しいだけでなく、日本の伝統行事とも深くつながっ
ているのが特徴。季節を感じながら、心にも響く食の体験ができるでしょう。
□■ 秋の味覚を堪能しよう ■□
美しい紅葉、涼しい気候、そして何よりも美味しい季節の食材。まさに秋は至福の時
期といえます。
11月の食卓には、松茸やサンマ、栗など、秋ならではの味覚がそろっています。そん
な旬の恵みをたっぷりと味わい尽くしてみませんか?
温かな料理を囲んで家族や友人と楽しむのも素敵ですし、一人でゆっくりと味わうの
もいいかもしれません。秋の夜長、心も体も満たされる至福のひとときを過ごしてく
ださいね。
みなさん、こんにちは!
そろそろ秋の気配を感じる季節になってきましたね。
9月といえば、敬老の日がありますよね。今年は9月18日(月)です。
おじいちゃん・おばあちゃんに「いつもありがとう」って気持ちを伝える絶好のチャンス!でも、どうやって過ごそうかな~って悩んでいる人もいるんじゃないでしょうか?
そこで今回は、敬老の日を楽しく、心温まる1日にするためのアイデアをご紹介します。一緒に素敵な思い出を作っちゃいましょう(^o^)/
1.昔話を聞いちゃおう!
おじいちゃん・おばあちゃんって、すっごく面白い話をたくさん持ってるんですよ。古いアルバムを見ながら「この写真、どんな時に撮ったの?」って聞いてみるだけで、びっくりするような話が聞けるかも。家族の歴史を知れるチャンスです♪
2.秘伝のレシピを教えてもらおう!
おばあちゃんの味って、なんであんなに美味しいんでしょうね。この機会に、大好きな料理のレシピを聞いちゃいましょう。一緒に作るのも楽しいですよ。きっと料理以外の人生の知恵も教えてくれるはず!
3.昔の遊びで一緒に遊ぼう!
お手玉やけん玉、知ってますか?意外と難しいんですよね。おじいちゃん・おばあちゃんに教えてもらいながら挑戦してみましょう。世代を超えた勝負、意外と盛り上がりますよ(^_^)
4.スマホマスターになってもらおう!
最近のスマホって便利ですよね。でも、おじいちゃん・おばあちゃんにとっては難しいかも。ビデオ通話の使い方を教えてあげれば、離れて暮らす家族ともっと簡単に話せるようになりますよ。SNSの使い方を教えてあげるのも良いかも。孫の日常をチェックできて喜んでくれるはず!
5.心のこもったプレゼントを贈ろう!
言葉で伝えるのが恥ずかしい…って人は、手作りのプレゼントはどうでしょう?手書きの手紙や、思い出の写真をまとめたアルバムなど、きっと喜んでくれるはず。特別な食事会を開くのも素敵ですね。おじいちゃん・おばあちゃんの好きなメニューで、サプライズパーティーなんていかがでしょうか?
6.地域のイベントに参加しちゃおう!
敬老の日って、地域でもいろんなイベントがあるんですよ。例えば、高齢者施設でのボランティア活動や、学校での交流イベントなど。おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に参加して、地域の人たちとも交流を深められたら素敵ですよね。
敬老の日は、おじいちゃん・おばあちゃんに感謝を伝えるだけじゃなくて、世代を超えた絆を深めるチャンスなんです。この日をきっかけに、普段からもっと会話を増やしていけたら素敵ですよね。おじいちゃん・おばあちゃんの経験や知恵って、本当に宝物。敬老の日を通じて、改めてその大切さに気づけたら良いですね。
宜しければ、おじいちゃん・おばあちゃんを誘って当店にご来店ください。
お待ちしています!(^_^)v